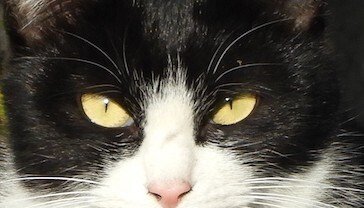松下幸之助一日一話
仕事の知恵・人生の知恵
1999年4月15日初版発行PHP文庫
松下幸之助翁に関しては、改めて紹介する迄も無く、よくご存じのことと思います。よって経歴等は省いて幸之助氏の「一日一話」から言葉をセレクトして紹介いたします。その言葉は平易な言葉を選んで語られていますが、内容は奥深く、仕事・経営・生き方等々、人生の指標になる言葉ばかりです。尚、個人的に好きな言葉を勝手に選ばさせていただいてます。ご興味ある方は、読みづらい内容とかまた、高価な本とか云う事はありませんので、原本を読まれることをお勧めいたします。
「一日一話」は昨年の七月から月一回、ランダムにピックアップして投稿していましたので、重複する部分も出てくると思いますが、暗記する迄に読んだ方が身に付くという事もあります。此れから新たな気持ちで一年間、幸之助翁の言葉を選んでいきたいと思います。
尚、冒頭の言葉、今回は、松下幸之助「人生心得帖」から選びました
「知識も大事、知恵も大事、才能も大事然し何よりも大事なのは熱意と誠意である。この二つがあれば、何事も成し遂げられる」―人生心得帖よりー
【二月の言葉】
*一日 天は一物を与える
この世に百パーセントの不幸と云うものはない。五十パーセントの不幸はあるけれども半面其処に五十パーセントの幸せがある訳だ。人間は其れに気付かなければいけない。兎角人間の感情というものは上手くいけば有頂天になるが、悪くなったら悲観する。是は人間の一つの弱い面だが其れをなるべく少なくして、いつの場合でも淡々とやる。信念を持っていつも希望を失わないでやることだ。天は二物を与えずと云うが、逆になるほど天は二物は与えないがしかし一物は与えてくれるということが言えると思う。其の与えられた一つのものを大事にして育て上げることである。
*二日 先ず好きになる
好きこそものの上手なれと云う言葉がありますがこれは商売についても当てはまります。商売を繁栄させたいと思えばまず自ら興味を持ち好きになることです。好きになれば努力することが苦にならない。寧ろ楽しくなる。そして唯お義理や飯の種にする為に事を運ぶと云うのではなく、誠心誠意其れに打ち込む。そこにこそ繁栄への一つの道があると思います。適材適所ということが言われますが、私は適材適所とはそういた商売の好きな人が商売に当るということであって、そうなれば千人が千人とも望みを達することも難事ではないと思うのです。
*六日 正しい国家意識
昨今の国際情勢は一方で世界は一つと云いつつも、その一方で各国が過度の国家意識に立ち自国の利害を優先して仕舞う為、対立や紛争が一向に絶えない。それでは日本はどうかと云うと、反対に国家意識が極めて薄い為却って問題が起こっている様である。個人でも正しい自己認識、人生観を生み出し自主性を持って生きていってこそそこに初めて他の人々に対しても奢らず、諂わず仲良く付き合っていける譯である。国でも同じことである。国民が正しい国家意識を持ち、他の国々と交流していくことが大切であろう。過ぎたるもいけないが及ばざるもいけない。
*七日 平穏無事な日の体験
体験と云うものは失敗なり成功為り何か事があった時だけに得られる、と云うものでしょうか。決してそうではないと思います。平穏無事な一日が終わった時、自分が今日やったことは果たして成功だったか失敗だったかを心して考えてみると、あれは一寸失敗だったな、もっといい方法があったのではないか。と云うようなことが必ずあると思います。それについて思いを巡らせば、これはもう立派な体験と云えるのではないでしょうか。形の上での体験だけでなく日々お互いが繰り返しいる目に見えない些細なことも、自らの体験として刻々に積み重ねていく姿勢が大切だと思うのです。
*九日 一歩一歩の尊さ
仕事はいくらでもある。あれも作りたい是も拵えたい、こんなものがあれば便利だ、あんなものも出来るだろうと次から次へと考える。その爲には人が欲しい資金が欲しいと願うことには際限がないが、一歩一歩進むより他に到達する道があろうか。それは絶対にない。やはり一歩一歩の繋がり以外に道はない。坦々たる大道を一歩一歩歩んでゆけばそれでよい。策略も政略もいらない。一を二とし、二を三として一歩一歩進んでゆけば遂には彼岸に達するだろう。欲しいと願う人も一人増えまた一人増えて遂には万と数えられよう。一歩一歩の尊さをしみじみと味わわねばならぬ。
*十日 同行二人
弘法大師さんが開かれた高野山にある霊場に詣でる人々の菅笠には皆一様に同行二人と書いてある。何処にいようと何処に行こうと自分は一人ぼっちではない。何時も御大師様と二人と云う意味である。つまりこれらの信仰三昧の人々の心の中には、今も御大師は生き生きと存在しておられるのである。勿論大師の生身の身体が其の儘ここにあると云う訳ではない。しかし大師は今も猶ここにおわすと感じることまた感じようと努める処に大師の教えが永遠に生きてくることに為る。真理は永遠に生きるということはこんな姿を言うのであろうか。
*十三日 一人の力が伸びずして
自分は一年にどれだけ伸びているか、技術の上に或は社会に対する物の考え方の上に、どれだけの成長があったか、その成長の度合いを測る機械があれば是は簡単に判ります。併し一人一人の活動能力と云うか知恵才覚と云うか、そういう総合の力が伸びているかどうかを図る機械はありません。けれども私は5%なり10%或は15%伸びたと自分で云えるようでないといけないと思います。やはり一人一人が自分の力でどれだけの事をしているかという事を反省してみることが大切です。一人一人の力が伸びずに社会全体の力が伸びると云う事はないと思うのです。
*十五日 自己観照
自省の強い人は自分と云うものをよく知っている。つまり自分で自分を善く見つめているのである。私は是を自己観照とよんでいるけれども、自分の心を一遍自分の身体から取出して外からもう一度自分と云うものを見直してみる。これが出来る人には自分と云うものが素直に私心無く理解できるわけであるこういう人には過ちが非常に少ない。自分にどれ程の力があるか自分はどれ程の事が出来るか、自分の適性は何か自分の欠点はどうした処に在るか、と云うようなことがごく自然に何物にも捉われることなく見出されてくると思うからである
*十十六日 最高責任者の孤独
組織のさお好責任者の立場に立つと部下は勿論、それまで同僚として一緒に働いてきた人々の自分に対する見方が変わってきます。自分は変わらなくとも周りでは見方が変わり、本当のことを言ってくれる親友と云うものは地位が上になればなるほど少なくなると云うのが現実ではないでしょうか。そういう意味で最高責任者は好むと好まざるとに拘らず心の上に色々な淋しさが出てきて、謂わば孤独な立場になるという事が言えます。だからこど所謂声なき声と云うものに耳を傾ける謙虚さと云うものがトップに立つ者にとって究めて大切だと思うのです。
*十七日 死も生成発展
私は人生とは生成発展つまり日々新たの姿であると考えています。人間が生まれ死んでいくと云う一つの事実は人間の生成発展の姿なのです。生も発展なら死も発展です。人間は今迄ただ本能的に死を恐れ忌み嫌い之に耐え難い恐怖心を抱いてきました。人情としては無理もない事です。しかし我々は生成発展の原理に目覚め、死は恐るべきことでも悲しむべき事でもつらい事でもなく寧ろ生成発展の一過程に過ぎない事、万事が成長する一つの姿であることを知って死にも厳粛な喜びを見出したいと思います。
*十八日 日本式民主主義を
民主主義の基本理念というものは真に好ましいものであり、これを取り入れ国家国民の調和ある発展繁栄を計っていくことは極めて重要なことだと云えます。けれどもそれは日本の伝統国民性と云うものに立って行わなくてはなりません。基本の理念は同じでも具体的な形態は其々の国民性に従って様々でなくてはなら・ない。謂わばアメリカにはアメリカ式民主主義フランスにはフランス式民主主義、日本には日本式民主主義がなくてはならないと思うのです。それを日本自らの伝統を忘れて、アメリカやフランスのようにやろうとしても、根無し草の民主主義に終わってしまうでしょう。
*二一日 人事を尽して天命を待つ
人事を尽して天命を待つと云う諺がある。是は全く至言で私は今も自分に時々その言葉を言い聞かせる。日常色々な面倒な問題が起きる。だから迷いも起きるし悲観もする、仕事に力が入らないことがある。是は人間である以上避けられない。しかしその時私は自分は是と信じてやっているのだから後は天命を待とう、成果は人に決めてもらおう・・こういう考え方でやている。小さな人間の知恵でいくら考えてみても、どうにもならぬ問題が沢山有り過ぎる。だから迷うのは当たり前である。そこに私は一つの諦観が必要だと思うのである。
*二三日 道徳は水と同じ
戦後の我が国では道徳教育というと何か偏った風に思われることが多いが、私は道徳教育はいわば水と同じではないかと思う。人間は活きる為にどうしても水が必要である。処がこの水に何か不純物が混じっていてそれを飲んだ人が病気になった。だからと云って水を飲むことを一切否定してしまったらどうなるか。大切なことは水そのものの価値効用を否定してしまうことではない。水の中の不純物を取り除くことである。嘗て道徳教育の中に誤った処があったからといって道徳教育そのものを否定してしまう事は其れこそ真実を知らぬことではないか。
*二五日 七十点以上の人間に
完全無欠な人間などあり得ないと思う。だからお互い人間として一つの事に成功することもあろうし、時には過ちもあるだろう。それは人間としてやむを得ないと云うかいわば当たり前の姿だと思う。併し過ちと正しい事を通算して正しい事の方が多くなる様な働き為り生活を持たなければやはり人間として、望ましい姿とは言えないのではなかろうか。仮に自分を点数で表すとどうなるだろう。三十点のマイナス面はあるが少なくともプラスの面が七十店あると云う様な処迄には到達するようお互い努力したいものである。
*二六日 時を待つ心
行き詰る会社を見てみますと大抵は仕事が暇に成ったら無理をしてでも注文を取ろうとしています。その結果却って大きな損をして会社の破綻を招く事になってしまうのです。反対に暇は閑で仕方ない。是は一時的な現象なのだからこの機会に日頃怠りがちだったお得意さんに対するサービスをしておこうとか、機械の手入れをすべきものはしておこうと云う様な態度をとっている会社は却って時を得て発展する。そういう場合が多い様に思います。中々難しい事ですが時を得なければ休養して時を待つ。そう云う心境も亦大事だと思います。
*二七日 誠意あればこそ
先般部品の一つに不良のある商品をお得意さんにお送りしてしまった時に、その方が厳重に注意しなければという事で会社に出向いてこられたことがあった。しかし実際に会社に来てみると、社員の人々が一心に仕事に打ち込んでいる姿を見て憤慨もせず却って信用を深めて帰られたと云う話を聞いた。この事から私は誠実且熱心に日々の仕事に力強く取り組むとという事が如何に大きなと唐を持っているかという事をつくづく感じさせられた。そういう態度と云うものは、見る人の心に何物かを与えるばかりでなく仕事とそのものの成果をより高める原動力にもなると思うのである。
*二八日 感謝の心は幸福の安全弁
感謝の念という事は是は人間にとって非常に大切なものです。見方によれば総ての人間の幸福なり喜びの根源とも云えるでしょう。従って感謝の心の無い処からは決して幸福は生まれてこないだろうし、結局は人間不幸になると思います。感謝の心が高まれば高まる程それに正比例して幸福感が高まっていく。つまり幸福の安全弁とも言えるものが感謝の心とも言える訳です。疎の安全弁を失ってしまったら幸福の姿は瞬時のうちに壊れ去ってしまうと云ってもいいほど人間にとって感謝の心は大切なものだと思うのです。