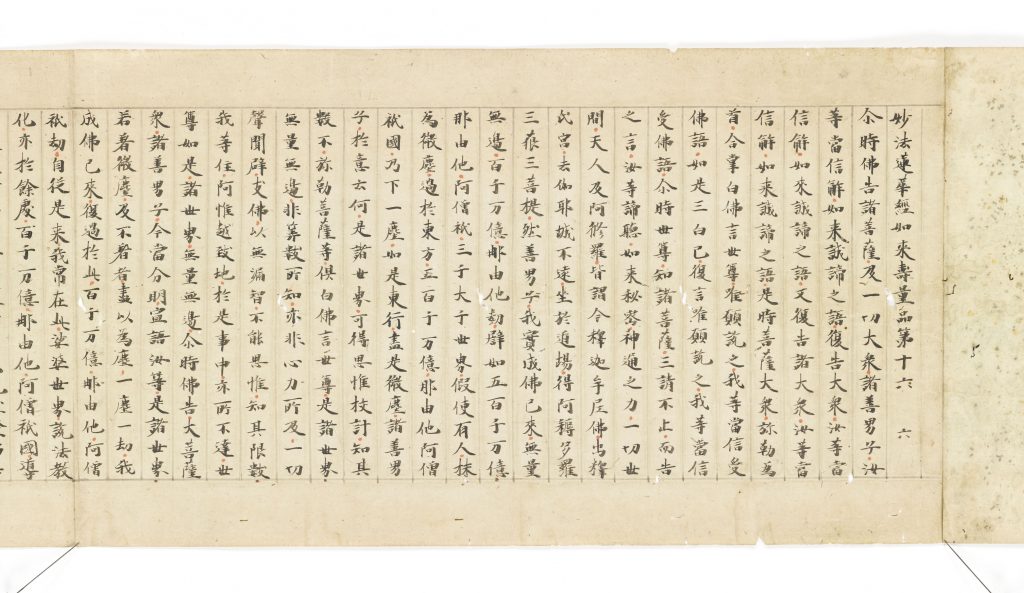=あいうえお順=
※ 新潮社古典文学集成古事記S54年度版による
※ 表記は 名前 読み方 巻 ページ 登場順にて表示
※ ページ数は新潮社古典文学集成54年版古事記による
※ 人名は同一人物の別記・別名また神名と重複するものも全て列記している
※ 普通名詞は個人として特定できるものは表記している
※ 人名表記総数は602 ☞ 内訳 序 12 上 1 中 370 下 219
全てを網羅したと思いますが、脱記があった場合はご容赦お願いします。人物の注記は 集大成の注記をも参考に 、古事記内で分かる最低限の説明にとどめています。古事記理解及び日本古代史の基礎知識として活用していただければ幸いです。尚、神名は参考にしている新潮社古典文学54年版「古事記」の末尾附録として掲載されてます。ご興味ある方は、そちらもご覧ください。
因みに 岩波古典文学大系「古事記」の付録は、今に伝わる祝詞のすべてが、また小学館版の「古事記」には上代歌謡のすべてが収録されています。

ア行
阿多小椅君 アタノオバシノキミ 中 119 35
鹿児島阿多地方豪族首長 アヒラヒメノ兄
阿比良比売 アヒラヒメ 中 119 36
アタノキミノ妹ジンムテンノウの妃 タギシミミ・キスミミノ母
県主波延 アガタヌシハエ 中 125 49
カワマタビメ兄 アクトヒメ(アンネイテンノウ妃)親
阿久斗比売 アクトヒメ 中 125 50
アガタヌシハエ娘・アンネイ妃
天押帯日子命 アメオシタラシヒコノミコト 中 126 65
コウショウテンノウ・ヨソタホビメ長子→春日臣・粟田臣・小野臣・柿本臣・壱比韋臣イチヒイ・大坂臣・阿那臣・多紀臣・羽栗臣・知多臣・牟耶ムギ臣・都怒山ツノヤマ臣・伊勢飯高臣・壱師臣・近ツ淡海國未造ノ祖
曙立王 アケタツノオホキミ 中 132 148
オホマタノオオキミ・エナツヒメ長子→伊勢品遅部君・伊勢佐那造ノ祖 スイニン朝ホムチワケ出雲大神詣副派遣 ヤマトハシキノトミノトヨアサクラノアケタツノオオキミ同
阿治佐波毘売(丹波) アヂサハビメ 中 132 155
イリネノオオキミ娘-オホツツキマワカノオオキミ妻
荒河刀弁 アラカハトベ 中 133 166
木ノ国造 トホツアユメマグハシヒメ(スジンテンノウ妃)親
阿耶美能伊理毘売 アザミノイリビメ 中 141 201
ヤマトタケル・ククマモリヒメ長子→鎌倉別・小津石代別・漁田イザリタ別の祖
阿耶美都比売命 アザミツヒメノミコト 中 141 203
スイニンテンノウ・アザミノイリビメ長女→イナセビコノオオキミ妻
足鏡別王 アシカガミワケノオオキミ 中 172 276
ヤマトタケル・ククマモリヒメ長子→鎌倉別・小津石代別・漁田イザリタ別の祖
淡海柴入杵 アウミノシバノイリキ 中 173 283
オウジンテンノウ・オトヒメ長女
阿倍郎女 アヘノイラツメ 中 184 313
オウジンテンノウ・オトヒメ長女
阿貝知能三腹郎女 アハチノミハラノイラツメ 中 184 314
オウジンテンノウ・オトヒメ次女
阿知吉師 アチシキ 中 192 345
百済照古王ノ命により応神朝来朝-横刀(七枝刀か-石上神宮)・大鏡献上→阿直史アチキノフビト等ノ祖
阿知使主 アチノオミ 中 192 350
漢直祖アヤノアタイノオヤ 応神朝帰化人漢人の統率者 (百済)
天之日矛 アメノヒボコ 中 197 354
新羅国皇子-来朝伝承→スイニン朝タジマモリの祖
阿加流比売神 アカルヒメノカミ 中 199 355
アメノヒボコ妻新羅より逃れて来朝難波比売碁曾神社祭神
秋山之下氷壮夫 アキヤマノシタヒヲトコ 中 200 368
秋山の擬人化→妻問伝承(古伝承集約化か)→大国主八上比売神話類型
ウミサチヤマサチ神話類型
葦田宿禰 アシダノスクネ 下 219 401
カツラギノソツヒコ(タケノウチスクメ六男)ノ子→クロヒメ(リチュウテンノウ妃)ノ父
青海郎女 アヲミノイラツメ 下 219 405
リチュウテンノウ・クロヒメ長女→ユウリャクテンノウ崩御後政為すか
イヒトヨノイラツメ・オシヌミノイラツメ・イヒドヨノオホキミ同 -臨朝秉政ミカドマツリゴトシタマヒ(顕宗天皇前紀)意祇王・袁祇王ノ姨オバ
阿知直 アチノアタイ 下 220 407
倭ノ漢ノ直アタイノ祖(オウジン朝帰化アチノオミ一族)
-スミノエナカツオオキミ謀反時リチュウテンノウ救出-後朝廷出納預かる→蔵ノ官
穴穂命 アナホノミコト 下 225 422
インギョウテンノウ・オオナカツヒメ三男→第二十代安康天皇アンコウ 石上穴穂宮-奈良天理市田町 56歳崩御 御陵:菅原伏見岡(奈良宝来町古城)
淡海之老媼 アフミノオミナ 下 259 468
淡海(近江)国の住人ーケンソウテンノウへ父オシハワケの遺骨の在処を教える功ニヨリ オキメノオミナの名を賜
天国押波流岐広庭命 アマクニオシハルキヒロニハノミコト 下 265 489
ケイタイテンノウ・タシラカミコト(ニンケンテンノウ女)長子-第二十九代欽明天皇キンメイ 師木島宮-奈良桜井市金屋初瀬川付近 書記:在位32年?御陵:檜隈坂合(奈良明日香村)
赤比売郎女 アカヒメノイラツメ 下 206 509
ケイタイテンノウ・ヤマトヒメ次女
阿倍波延比売 アヘノハエヒメ 下 265 510
地方豪族首長娘かまたは一族巫女か
阿都王 アツノオホキミ 下 265 513
ケイコウテンノウ・アヘノハエヒメ三女
足取王 アトリノオホキミ 下 267 537
キンメイテンノウ・キタシヒメ次男
漢王 アヤノオホキミ 下 269 586
帰化人氏族首長か オホマタノオホキミ(ホコヒトヒツギノミコ妃)兄
イ行
稲幡之八上比売 イナバノヤカミヒメ 上 58 13
因幡巫女 大国主妻 木俣神(御井之神)親
五瀬命 イツセノミコト 中 108 15
神武天皇異母兄 東征の折トミビコの矢を受て戦死
井氷鹿 イヒカ 中 113 22
神武東征援 土人吉野首ノ祖(神名)
石押分之子 イワオシワク 中 114 23
神武東征援 吉野豪族生尾族 吉野ノ國巣ノ祖(神名)
飯日比売命 イヒヒヒメノミコト 中 125 60
シキノアガタヌシの祖 フトマワカヒメノミコト同 イトクテンノウ妃
伊迦賀色許売命 イカガシコメノミコト 中 128 89
ウツシコヲ娘-コウゲンテンノウ妃・カイカテンノウ庶母後カイカテンノウ妃
伊理泥王 イリネノキミ(オオキミ) 中 131 147
ヒコイマスオオキミ・ヲケツヒメ三男 アヂサハビメ(オホツツキノマワカ妻)ノ母
伊玖米入日子伊沙知命 イクメイリヒコイサチノミコト 中 133 178
スジンテンノウ・ミマツヒメ長子→第十一代垂仁天皇スイニン 師木玉垣宮-奈良桜井市穴師
153歳崩御 御陵:菅原御立野ミタタシノ中(奈良市尼辻附近)
伊耶能真若命 イザノマワカノミコト 中 134 177
スジンテンノウ・ミマツヒメ次男
伊賀比売命 イガヒメノミコト 中 134 180
スジンテンノウ・ミマツヒメ三女
活玉依毘売 イクタマヨリビメ 中 135 184
スエツミミ娘(茅淳県陶邑チヌノアガタスエムラ―現大阪堺市ノ豪族か)大物主大神妻
飯肩巣見命 イヒカタスミノミコト 中 135 186
クシカタノミコト子-オオモノヌシ系
伊迦賀色許男命 イカガシコヲノミコト 中 135 188
スジンテンノウ命により大神神社神事準備
印色之入日子命 イニシキノイリヒコノミコト 中 141 193
スイニンテンノウ・ヒバスヒメ長子→灌漑事業・横刀壱千口石上神社奉納 河上部制定
伊賀帯日子命 イガタラシヒコノミコト 中 141 200
スイニンテンノウ・ヌバタノイリビメ次男
伊許婆夜和気命 イコバヤワケノミコト 中 141 202
スイニンテンノウ・アザミノイリビメ長子→沙本ノ穴太部アナホベ別ノ祖
五十日帯日子王 イカタラシヒコノオオキミ 中 141 209
スイニンテンノウ・カリハタトベ次男→春日ノ山君・高志ノ池君・春日部君ノ祖
伊登志別王 イトシワケノオホキミ 中 141 210
スイニンテンノウ・カリハタトベ三男→伊登志部-部曲カキベ制定
石衝別王 イハツクワケノオホキミ 中 141 212
オスイニンテンノウ・オトカリハタトベ長子→羽咋君・三尾君ノ祖
石衝毘売 イハツクビメ 中 141 213
オスイニンテンノウ・オトカリハタトベ長女→倭建命妃
稲瀬毘古王 イナセビコノオオキミ 中 142 215
スイニンテンノウ娘アザミツヒメノ夫
五百木入日子命 イホキノイリヒコノミコト 中 154 234
ケイコウテンノウ・ヤサカノイリヒメ次男(太子) シリツキトメ妻☞ホムダノマワカノ親 中日売(オウジンテンノウ皇后・仁徳天皇生母)祖父
五百木入日売命 イホキイリヒメノミコト 中 154 236
ケイコウテンノウ・ヤサカノイリヒメ長女
伊那毘能若郎女 イナビノワカイラツメ 中 155 247
イナビノオオイラツメ(ワカタケキビツヒコ娘・ケイコウテンノウ妃)妹-ケイコウテンノウ妃
磐鹿六雁※ イワカムツカリ 中 157 259
※膳臣ノ祖―ケイコウテンノウ朝白蛤ウムギ献上→膳ノ大伴部―宮廷料理部族、後の高橋氏一族
出雲建 イヅモタケル 中 160 261
雲国豪族勇者→ヤマトタケルノ智謀ニヨリ征伐サル
稲依別王 イナヨリワケノオホキミ 中 172 271
ヤマトタケル・フタジヒメ長子→犬上君・建部君等の祖
飯野真黒比売命 イヒノノマグロヒメノミコト 中 172 279
クヒマタナガヒコ(オキナガタワケ子)ノ長女-ワカタケル妻
伊佐比宿禰 イサヒノスクネ 中 179 297
難波吉師部キシベ臣の祖-反逆軍忍坂王軍の将
伊奢之真若命 イザノマワカノミコト 中 183 307
オウジンテンノウ・タカギノイリヒメ三男
糸井比売 イトイヒメ 中 184 326
シマタリネ娘-オウジンテンノウ妃
伊奢能麻和迦王 イザノマワカノオホキミ 中 185 339
オウジンテンノウ・カツラギノノノイロメ長子
伊豆志袁登売 イヅシヲトメ 中 200 367
アメノヒボコ系譜帰化人かー伊豆志大神娘(巫女)ハルヤマノカスミヲトコノ7妻
伊和島王 イワジマノオホキミ 中 203 381
ネトリノオオキミ・ミハラノイラツメ次男
石之日売命 イハノヒメノミコト 下 204 383
カツラギノソツヒコ(タケノウチスクネ六男)娘 →ニントクテンノウ后
市辺忍歯王 イチノヘオシハノオオキミ 下 219 403
押歯王 リチュウテンノウ・クロヒメ長子-ケンソウ・ニンケンテンノウ父→ユウリャクテンノウにより弑
飯豊郎女 イヒトヨノイラツメ 下 219 406
リチュウテンノウ・クロヒメ長女→ユウリャクテンノウ崩御後政為すか アヲミノイラツメ・オシヌミノイラツメ・イヒドヨノオホキミ同 -臨朝秉政ミカドマツリゴトシタマヒ(顕宗天皇前紀)意祇王・袁祇王ノ姨オバ
飯豊王 イヒトヨノオホキミ 下 255 460
リチュウテンノウ・クロヒメ長女→ユウリャクテンノウ崩御後政為すか アヲミノイラツメ・イヒトヨノイラツメ・オシヌミノイラツメ同
石木王 イハキノオホキミ 下 256 466
不詳 地方豪族か
出雲郎女 イヅモノイラツメ 下 264 484
ケイタイテンノウ・ワカヒメ長女
石比売命 イシヒメノミコト 下 266 518
センカ(センゲ)テンノウ・タチバナノナカツヒメ長女→キンメイテンノウ妃
石垌王 イハクマノオホキミ 下 267 536
キンメイテンノウ・キタシヒメ長女
伊美賀古王 イミガコノオホキミ 下 267 541
キンメイテンノウ・キタシヒ五男
伊勢大鹿首 イセノオホカノオビト 下 269 567
伊勢地方豪族首長か ヲグマコノイラツメ(ビタツテンノウ妃)親
飯女之子 イヒメノコ 下 270 599
タギマノクラノオビトノヒロ娘-ヨウメイテンノウ妃
ウ行
宇佐津比古 ウサツヒコ 中 108 16
土人クニビト大分宇佐豪族
宇佐津比賣 ウサツヒメ 中 108 17
土人クニビト大分宇佐豪族
宇麻志麻遅命 ウマシマジノミコト 中 119 34
ニギハヤヒ・トミビメの子-物部連・穂積臣・婇臣ノ祖
内色許男命 ウツシコヲノミコト 中 128 84
穂積臣等祖 妹ウチシコメノミコト(コウゲン妃) ウマシマジノミコト末裔物部氏同祖
内色許女命 ウツシコメノミコト 中 128 85
ウツシコヲ妹-コウゲンテンノウ妻
味師内宿禰 ウマシウチノスクネ 中 129 98
ヒコフツオシノマコトノミコト・タカチナビメ(オホナビ妹)長子 山代ノ内ノ臣ノ祖
宇豆比古 ウヅヒコ 中 129 99
木ノ国造ノ祖 妹ヤマシタカゲヒメ(ヒコフツオシノマモトノミコト妻)
菟上王 ウナカミノオホキミ 中 132 149
オホマタノオオキミ次男→比売陀君野祖 スイニン朝オムチワケ出雲大神詣副派遣
歌凝比売 ウタゴリヒメ 中 152 222
タニハ(旦波―丹波)ミチノウシオオキミ娘ーホムチワケ育児係実家へ還
宇遅能和紀郎子 ウヂノワキイラツコ 中 184 319
オウジンテンノウ・ミヤヌシヤガワエヒメ長子(長女)→太子詔勅 オホサザキと皇位を譲り合い早逝する
宇遅之若郎女 ウヂノワカイラツメ 中 184 323
オウジンテンノウ・ヲナベイラツメ長女 ニントクテンノウ后(庶妹)
菟田首 ウダノオビト 下 256 463
オフヲ(ヲケノミコ妻)親
馬来田郎女 ウマグタノイラツメ 下 265 497
ケイタイテンオウ・クロヒメ三女
馬木王 ウマキノオホキミ 下 268 549
キンメイテンノウ・オエヒメ(ソガノイナメ妹・キタシヒメ長子
菟道貝蛸皇女 ウヂノカヒタコノヒメミコ 下 268 557
ビタツテンノウ・トヨミケカシキヤヒメ(後のスイコテンノウ)長女ーショウトクタイシ妃
シヅカヒノオホキミ・カヒタコノオホキミ・ウヂノシヅカヒ同
菟道静貝皇女 ウヂノシヅカヒ 下 268 558
ビタツテンノウ・トヨミケカシキヤヒメ(後のスイコテンノウ)長女ーショウトクタイシ妃 シヅカヒノオホキミ・カヒタコノオホキミ・ウヂノカヒタコノヒメミコ同
宇毛理王 ウモリノオホキミ 下 268 563
ビタツテンノウ・トヨミケカシキヤヒメ(のちのスイコテンノウ)四男
宇遅王 ウヂノオホキミ 下 269 576
ビタツテンノウ・ヒロヒメミコト三男
上宮厩戸豊聡耳命 ウエノミヤノウマヤドノトヨトミミノミコト 下 270 594
ヨウメイテンノウ・ハシヒトアナホベオホキミ長子-スイコテンノウ摂政→聖徳太子ショウトク